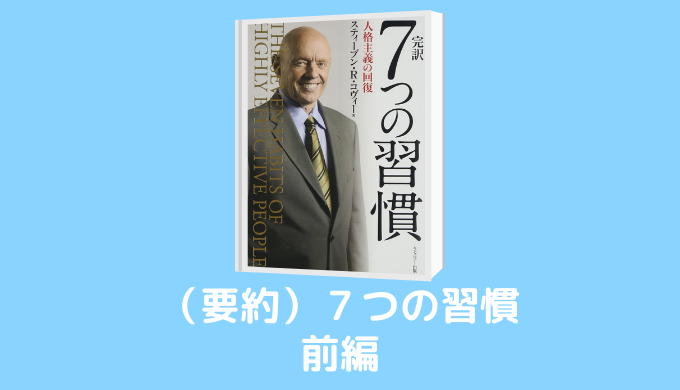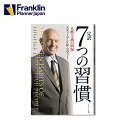悩んでる人
悩んでる人
この記事で学べるコト
- ”本当の成功者”になるための心得
- 「7つの習慣」の原則
- 私的成功のための3つの習慣

自分の運命を自分で切り開くための奥深いアドバイスをわかりやすく教えることに生涯をささげ、タイム誌が選ぶ世界で最も影響力のあるアメリカ人25人のひとりに選ばれている。
著書『7つの習慣』は全世界で販売部数3,000 万部を記録し(40カ国語に翻訳)、20 世紀に最も影響を与えたビジネス書の 1位に輝いている。
ユタ州立大学商経学部終身教授、リーダーシップ学において同大学の名誉職ジョン・M・ハンツマン・プレジデンシャル・チェアに就く。
目次
本当の成功とは何か

成功の定義
「7つの習慣」での「成功」とは、単にお金持ちになるとか、仕事で出世するとか、周りのライバルに勝つという表面的なものではありません。
人生において本当に大切だと思うものは、一人ひとり異なるはずです。
それを見極め、手に入れて、心の底から充実感を得る。それを「7つの習慣」では「成功」と呼んでいます。
「人格主義」こそが成功のカギ
「人格主義」とは以下のような、人間の内面にある人格的なことを大切にする考え方。
- 誠意
- 謙虚
- 誠実
- 勇気
- 忍耐
- 勤勉
- 質素
- 節制など
つまり、「7つの習慣」とは、「人格」をみがくための習慣であり、人格をみがくことで、わたしたちは「本当の成功」を手に入れることができる、というわけです。
現代は個性主義にとらわれ過ぎている
対する「個性主義」とは、以下のようなテクニックなどにより人間関係を円滑にすることによって成功とする考え方。
- 個性
- 社会的イメージ
- 態度
- 行動
- スキル
「7つの習慣」の使い方
「7つの習慣」には7つの身に付けるべき習慣がありますが、1つめの習慣から積み上げることで全体の効果が高まってきます。
ある習慣は土台になり、ある習慣はその土台の上で大きな効果を発揮して、ある習慣は全体を補っている。
という感じで、習慣どうしが関係しあって、あなたを大きく成長させ、成功へ導いてくれます。
1つずつの習慣を丁寧にこなしていきましょう!
さて、成功への準備はできていますか?早速見ていきましょう。
「7つの習慣」の原則

原則1:パラダイムシフト
わたしたちは、育った環境や経験・知識を積み重ねることで、物事を主観や先入観で判断してしまいがちです。これをパラダイムと呼びます。
「うまくいっていないな」と感じれば「うまくいっている」状況に変えるためには、パラダイムを変えていかないといけないのです。
ものの見方を変えることを、パラダイムシフトと呼びます。

![]() あなた
あなた
![]() 相手
相手
![]() 相手
相手
多くの人は答えがひとつだと、いったん思い込んでしまったら、そのパラダイムを変えるのは難しいのです。
どうやってパラダイムシフトを起こすのか
「原則」に基づいたものの見方に近づけることです。
誰だってウソをつくより正直でありたいし、誰かの役に立ちたいと思うはずです。
原則2:インサイド・アウト
「インサイド」とは、自分の内側、「アウト」は周りの環境や相手を示します。
まわりの環境や、相手を変えることは誰にもできません。
できるのは、自分の内側から変わり、まわりに影響を与えていくことです。
内側から変わるためには「パラダイムシフト」が必要になってきます。
「7つの習慣」の構成

私的成功
第1~3の習慣は、地面で根を張り、土台となっています。
人間でいうなら、外に出ていない自分の内面が磨かれ、自立して生きる状態を指しています。これを「私的成功」と呼びます。
公的成功
地上に出て木として見える幹や枝葉の部分が第4~6の習慣です。
人間でいうなら、社会や人間関係にあたる、まわりの人たちとの協力・助け合いによって大きな成果を生む状態を指しています。これを「公的成功」と呼びます。
木全体を成長させる
そして木全体を成長させてくれる存在が第7の習慣です。
それぞれの習慣についてみていきましょう!
私的成功の3つの習慣
習慣1:主体的である
主体的=一時停止ボタン

主体的である1つ目の方法は、刺激を受けたときに自分の中で「一時停止ボタン」を押すことです。
わたしたちは反応的に行動するのではなく、どう行動するのかを主体的に選ぶことができ、まわりに振り回されず、人生を自分のものにすることができます。

新しい「キーボード」を購入しようと秋葉原に出かけた少年A。
ところが、欲しいキーボードがなかなか見つからず、不意に目にとまった「マウス」を発見。
「これカッコイイ」と即買した。

新しい「キーボード」を購入しようと秋葉原に出かけた少年B。
同じく欲しいキーボードがなかなか見つからず、不意に目にとまった「マウス」を発見。
少年Bは「ここでお金を使ったら後で見つけたキーボードが買えなくなるかも」と一時停止。
それでも「このマウスが絶対に欲しい」と納得してからマウスを購入した。
2つの例は、結果は同じだったとしても、結果までのストーリーは全く違います。
反応的な例では、自分の物欲から衝動買いしてしまっています。
もし、後で本当に欲しいモノがあって買えなくなってしまったら、この人は後悔するかもしれません。
しかし、主体的な人は、納得して諦めることができるはずです。
「影響の輪」を意識する
主体的であることで、自分を変えることはできますが、自分の力では変えられないものもあります。

自分の力で変えることができる範囲を「影響の輪」と呼びます。
逆に自分の力では変えることができないものを「関心の輪」と呼びます。
事実、主体的でない人ほど、変えられないものに多くの時間とエネルギーを注いでしまっていることが多いです。
自分の力ではどうにもならないことに、くよくよ悩んでいませんか?腹を立てていませんか?
自分が行動することで変えられる「影響の輪」に全集中しましょう!
習慣2:終わりを思い描くことから始める
ゴールがないのは設計書がない建築と同じ
主体的に行動できるようになっても道に迷ってしまう事があります。
それはまだゴールが描けていないためです。
もし、家を建てようと思ったらまず設計書を作成します。
設計書とは、「目指すべきゴール」が記されています。
もし設計書のないまま家を建ててしまったら、、これは考えるまでもなく、作業は迷いの連続になりますね。

終わりを描くことから考えることができれば、数ある選択肢から、自信をもってそのうちの1つを選択できるようになるのです。
ブレない価値観(原則)を定めよう
 悩んでる人
悩んでる人
少年Aは部活の大会を控えた高校2年生。
彼は来年の受験に備え、模擬試験が来月まで迫っているが、どちらも手を抜けずに困っていた。
このように人はいくつもの役割があります。
「部員としての私」「受験生としての私」「友人としての私」「家族としての私」など。
役割ごとにゴールを持っている場合、気持ちがブレてしまう事があります。
そこで重要なのが「原則」を中心に考えることです。

改めて「原則」とは、「誠実」「構成」「貢献」「可能性」「成長」などの、人がもともと「こうありたい」と願っている望みのことですね。
原則を中心に役割やゴールを設定することで、自分を俯瞰して眺めることができるようになります。
そして自分にとっての原則を定め、それぞれの役割のゴールを宣誓してみましょう。

内容や書き方に決まりはありませんが、自分にとっての「原則」と「ゴール」はじっくり考えて書いてみてください。
習慣3:最優先事項を優先する
 悩んでる人
悩んでる人
そこで必要になってくるのが、自分とって最も大切なこと「優先事項」を優先する考え方であり、それが第3の習慣です。
最優先事項を見える化しよう
まず下の図をご覧ください。

「第1領域」は”やらなければならない”という、自動的に反応し、行動しているパターンがほとんどです。
「第2領域」は緊急性はありませんが、自己啓発や副業など、「人生のゴール」を実現するために必要な領域であり、「第2領域」が最も優先すべき事項なのです!
「第3領域」は、急な雑務など、緊急性は高いものの、人生のゴールを見ると、それほど重要とは言えません。
「第4領域」は、時間を消費する行動:ヒマつぶしや娯楽(YouTubeやスマホゲームなど)が該当し、「なりたい自分」や「人生のゴール」に近づくことはまずありません。
しかし、非常に多くの人は「第4領域」に多くの時間を使っているのではないでしょうか。
まずは「やるべきコト」「やりたいコト」を各領域に当てはめて書き出してみてください。
「第2の領域」に時間を捧げるためには

 悩んでる人
悩んでる人
 ひぐらし
ひぐらし
- 必要な時には勇気をもって断る
- 人の力を借りる
必要な時には勇気をもって断る
第2の時間を確保するためには、その他の領域の時間を犠牲にしなくてはいけません。
第1の領域は、緊急かつ最優先ですから、犠牲にはできません。
第3、第4の領域の時間を削ることを考えます。
「遊びの誘い」「残業依頼」「飲み会の誘い」などは、第1の習慣「主体的に考える」、第2の習慣「ゴールから考える」を実践してきたあなたなら、今何が重要であるかを判断でき、その時の状況に応じて断ることができると思います。
人の力を借りる
自分ができることには限りがあるので、思い切って人にお願いするのも1つの手段です。
もちろん、自分でやることに価値があることは自分で実施すべきですが、自分で実施する必要のない用事や、知識のある方と一緒に行動した方が早い場合も、もちろんあります。
相手が伸び伸びと作業できるよう、依頼する場合は、相手を信頼してやり方を任せることが重要です。
前半パートまとめ
習慣1のポイント
- 「一時停止ボタン」を押して行動を選ぶ
- 「影響の輪」にあるエネルギーに全集中する
習慣2のポイント
- ゴールを決める
- 自分の中心となる「原則」を考える
習慣3のポイント
- 「第2の領域」に人生を捧げよ
- 「第2の領域」を優先するために「断る」「まわりの力を借りる」
主体的な考え方で、ゴールを定め、優先順位を決めて、自分の原則に従って行動することで「私的成功」を得られるということを紹介いたしました。
何が一番重要かを見極められれば、余計なことをしなくていいので、時間と体力に余裕が生まれます。
余裕は、自分の考えを持ったり、重要な事にゆっくり時間を使えることにつながるので、とてもイイ循環が生まれることでしょう。
後半パートでは、「公的成功」のための習慣と、成功を繰り返すための第7の習慣についてまとめていきます。